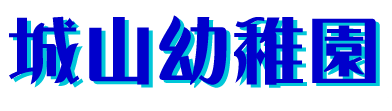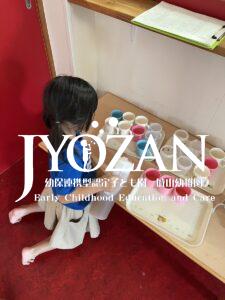先日、幼稚園連合会の研修大会というものがあり、発表させて頂く機会がありました。
以前、園長のブログにもありましたが、今日は発表者がブログを綴ります。
熊本大会と九州大会(福岡)があり、どちらも約100人の先生方の前での発表という事で、大緊張でしたが無事に終える事が出来ました。
発表のテーマは「環境を通した保育の実践」とし、実践発表という形で行いました。
日々の保育で行っている異年齢保育、チーム保育、ゾーンの構成、保育方法(選択性の保育、順序性の保育、習熟度別保育)を中心に話をしました。
もちろん、ランチや「やりたくない子たちの気持ちも保障する環境作り」も話しをしましたよ。
私たちも日々の保育を振り返りながら、環境を整えているところです。
以前から「環境を通した保育を行わなければならない」と考えられている乳幼児教育ですが、最近さらに意識されるようになりました。
子ども達は、子ども同士の関わり合いの中でたくさんの力が育まれていきます。
子ども達が遊びの中での学びを体験、経験していくために環境を整えなければなりません。
そこには子どもたちの自発性や主体性が大切・・・
いかに子ども達が主体的に環境に働きかける事ができるか・・・
将来、子ども達が豊かな気持ちが育つようにも乳幼児期の「今」の環境が大切ですね。
今後ますますAI化が進み社会情勢が変化していく中で、今を生きる子ども達に何ができるのかをしっかりと考える必要があります。
発表までの数か月、日々の保育を振り返りながら、改めて「見守る保育」を勉強し、発表データをまとめたり、動画を撮って考察・研究を繰り返す中で学びがさらに深まりました。
その深めた事をさらに学びに変えるのがアウトプット。
今回は私立幼稚園や認定こども園の先生方に伝える事で更に学びが自分の中に蓄積されたように感じます。
自園での取り組みや保育方法をわかりやすく伝えるためにはどうしたらよいか?
自分たちが普段から当たり前に行っている「環境を通した保育」をどこまで掘り下げて話すのか?
毎日のように悩みましたが、、、
九州大会終了後、参加された先生方よりたくさんの感想も頂戴し、少しは意図した部分が伝わったかな?とありがたく、嬉しい気持ちにもなりました。
学びを深めるアウトプット。
日々の保育に自信を持って発信する事の大切さも改めて感じる事ができました。
また、藤森メソッド提唱者であられる、藤森平司先生にも助言者として東京より来ていただき、貴重なお話をたくさん聞く事ができ、なかなか無い濃密な時間を過ごさせて頂きました。
この学びを子ども達、保護者の方々、職員へしっかりと還元できるように日々の保育をより楽しみたいと思います。
☆だんごむし★