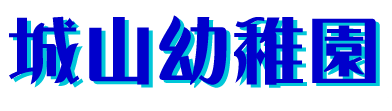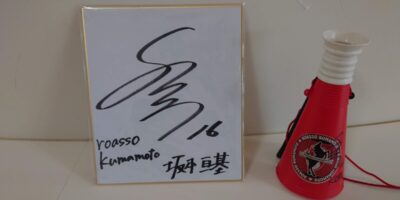先日熊本市から、「架け橋期のカリキュラム」作成についてという依頼文が届きました。
大量の資料と共に…
主旨としては、幼児教育と小学校教育の教育課程や構成原理において違いがあるにも関わらず、現場の相互理解ができていないため、
その課題を解決するためのものとのこと。
具体的に課題点として、このようなこと書かれていました。
※遊びを通して学ぶという幼児期の特性に関する認識が、社会的に共有されているとは言い難く、幼児教育については、
いわゆる早期教育や小学校教育の前倒しと誤解されることがある。
もっともなことが書かれていました!
これは幼児教育の現場からも是非、参画しなければ!
ということで、今後近隣の小学校と協力して、年長児から小学校1年生への架け橋期カリキュラムを作成することになると思います。
さて、先日保護者のみなさまにはお知らせしておりました通り、7月24日に行われました【熊本県私立幼稚園研修大会】にて、
当園の職員が実践発表を行いました。ちなみに今週は、その九州大会での発表も控えていますが…

【環境を通した保育の実践】当園の日々の保育で大事にしていることがぎゅっと凝縮されたプレゼンでした。
その助言者として、当園が実践する【藤森メソッド 見守る保育】の提唱者である 藤森平司氏に来ていただきました。
その助言の中に、まさにこの幼保小連携が以前とは全く変わり、小学校の教育改革が進んでいるというお話がありました。
それこそ以前は、小学校側から私たちの幼稚園・保育園・こども園に対しては…
「きちんと座れるようにしておいてください。」など要望ばかりでした。
それが、先日東京のある小学校における幼保小連携において、小学校側が話す内容が全く違っていたようです。
1年生担任からの報告…
「生活科の授業は総合的な学びの基礎であり、その指導を通して、幼児期の学びの基礎の重要性を実感している、
いかに幼児期に遊びこんでいるかが重要で、遊びこんでいる子たちの方が学校で色んな勉強ができる」
他にも…
「今までは1年生を赤ちゃん扱いする雰囲気があったが、最近まで園ではリーダーだったのだから、できるだけできる存在として捉え直すような
働きかけをしている」
「もし子供が困っている時には先生が、「園ではこういう時にはどうしていたの?」と聞くようにし、園での経験を尊重するようにしている。
あーしなさい、こーしなさいではなく、「園ではどうしていたの?」という問いかけをするようにしている。そういう意味で、園での経験を尊重している。
さらに授業では、自分の意見を言えることを重視している。」
かなり進歩です。
私たちが目指す保育からの学校教育が形になり始めているようで、ワクワクします☆☆☆
HOKARI TOYODA